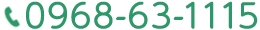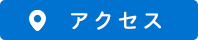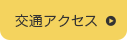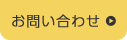病理検査室とは、患者さんから採取された臓器や組織、細胞から顕微鏡標本を作製し、癌などの病気を正確に診断する部門です。
病理検査室の業務は主に1)病理組織検査、2)細胞診検査、3)術中迅速検査、4)病理解剖に分けられます。
病理検査の現場には病理診断科の常勤病理医2名、非常勤病理医1名と臨床検査技師3名が在籍しておりこれらの業務を連携し行っています。
1.病理組織検査
胃カメラや大腸カメラ等の内視鏡検査で採取される小さな組織片(生検)から、手術で摘出される臓器(手術検体)まで様々なものが対象となります。
生検では病変の種類を確定診断する検査でその後の治療法を決定するのに重要な情報となります。
手術材料の検査では腫瘍の大きさ、悪性度、転移の有無などが判定され、①進行度(広がり・深さ)、②治療効果の判定、③再発の可能性の予測などを総合的に評価し、形態学的に診断を行います。
診断は病理医が行い、臨床検査技師はそのための組織標本作製を担当しています。
切り出し作業

切り出し作業-
手術で摘出した大きな組織は、顕微鏡で観察できる程度の大きさに標本を作る必要があります。肉眼的に詳しく観察し、標本を作るための適切な部位をいくつも切り採ります。
パラフィン浸透器

パラフィン浸透機(自動固定包埋装置)-
切り出した組織を薄くスライスする(薄切)ために、組織の中の水分を取り除き(脱水)、溶かしたパラフィン(ロウを溶かしたような温かい液体)を浸透(パラフィン浸透)する操作を一つの処理槽内で一晩かけて自動的に行う装置です。
パラフィンブロックの作製

パラフィンブロックの作製(包埋装置)-
溶かしたパラフィンの中に組織を埋め込み、冷やしてパラフィンを硬化させブロック状にしたもの(パラフィンブロック)を作製します。このパラフィンブロックはコンパニオン診断(お薬の効果を投与前に予測するために行う検査)にも利用されており半永久的に保存が可能で当院では30年保管しています。
薄切作業

薄切作業-
顕微鏡で観察できるようにパラフィンブロックをミクロトームと呼ばれる器具で極薄に薄切します。ミクロトームの上部には替刃が付いており上部を滑らせることで3~4μm(1μm=1/1000mm)程にスライスし、それをスライドガラスに貼り付けてスライド標本としています。
これらの工程は繊細な作業で、多くが手作業で行われており、病理医の的確な診断に適した良質な標本作製に努めています。
自動染色装置

自動染色装置-
薄切作業で作製されたスライド標本は顕微鏡で観察しやすいように染色しています。染色は自動化され、主に病理組織学的診断の基本的な染色法であるヘマトキシリン・エオジン染色(HE染色)を行っています。
必要に応じて特殊染色、免疫組織化学染色やコンパニオン診断のための遺伝子検査等を実施しています。特殊染色は院内で、免疫組織化学染色やコンパニオン診断のための遺伝子検査等は外注で対応しています。診断結果は主治医に届けられ、より特異的・効果的な治療の選択につなげています。
2.細胞診検査
顕微鏡で異常な細胞をみつけだし、細胞レベルで診断する検査です。
尿・喀痰・胸水・腹水などに剥がれ落ちた細胞や、子宮頚部・子宮内膜の粘膜からこすり取ってきた細胞、また乳腺・甲状腺・リンパ節などの体の表面に近い臓器の病変が疑われる部位を超音波(エコー)にて画像を確認しながら細い針を刺して採られた細胞などをスライドガラスに塗りつけます。
自動染色装置

自動染色装置-
塗抹標本は顕微鏡で詳細に観察ができるように染色しています。染色は自動化しており、細胞診検査ではパパニコロウ染色を主に行っています。
鏡検

鏡検-
染色標本を光学顕微鏡で観察し病気の有無を診断します。鏡検は細胞検査士という資格を持つ臨床検査技師が病理医の指導のもとで行っています。
主にがん細胞(悪性細胞)があるかどうか、もしくは悪性を否定するために行われますが、経過観察やがん検診にも利用されており、時に感染症の有無や炎症などの診断にも役立ちます。
3. 術中迅速診断
手術中に提出された組織を急速に凍結し、クリオスタットという特殊なミクロトームを用いて短時間(約15分)で標本作製し、病理医が診断を行います。手術中に結果を報告することで良・悪性の鑑別・切除断端の評価や、術式決定の一助となっています。
クリオスタット

クリオスタット-
クリオスタットは急速に凍結したブロックを薄切することができます。術中迅速検査では、生の検体(組織)を扱うため検査技師が病原体などに暴露される危険が懸念されます。そのため、このクリオスタットではバイオハザード対策としてオゾン処理機能やバキューム機能を搭載しており庫内を清潔に保つことができ作業環境に配慮されています。
安全キャビネット

安全キャビネット-
生の組織や細胞など感染性のある検体を取り扱う際に使用します。作業空間(箱状の作業台)が陰圧となっているため外の空気が作業空間の方へ流れ込み、汚染した空気はHEPAフィルターを通して清浄化され排出されているため感染が広がることを防いでいます。また、作業後は紫外線灯(UV)を点灯し、作業空間を殺菌することができます。
局所排気装置

局所排気装置-
主に染色、封入などの作業時におけるキシレン蒸気の除去をしています。局所的な気流を作ることで室内に有機溶剤(主にキシレン)などの有害物質を拡散する前に排出することができるため検査技師への健康障害防止として対策しています。
4. 病理解剖
残念ながら亡くなられた患者様のご遺体に対して、ご遺族の承諾のもとに、①亡くなられた経過と直接の死因、②治療効果の判定、③生前の診断の妥当性等の解明のために行う解剖(剖検)です。
生前の診断・治療の客観的な評価を行う最後の機会として、医療の中で重要な位置づけとなります。
病理解剖を行った症例についてはCPC(臨床病理カンファレンス)を行っており、主治医と病理医のほか、看護師・薬剤師・臨床検査技師など多職種が参加し、患者様の生前の御苦労に報いるためにご遺族の崇高な決意を無駄にすることのないよう、また医学の進歩に少しでも寄与できるよう努めています。
各種認定資格取得状況(臨床検査技師)
細胞検査士 3名
国際細胞検査士 1名
認定病理検査技師 1名
有機溶剤作業主任者 1名
毒物劇物取扱責任者 1名